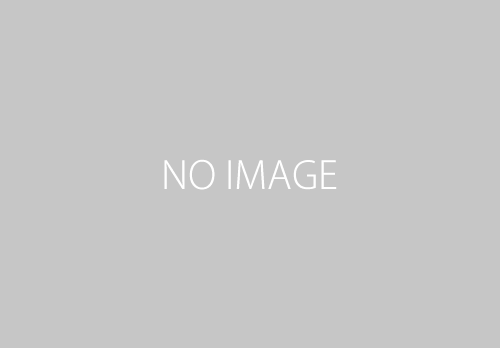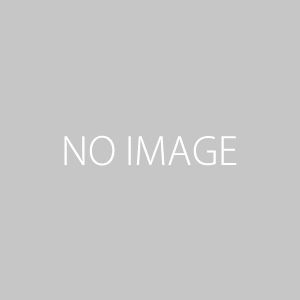11/24(金)ドキュメンタリー映画『JULLAY 群青のラダック』野村展代監督インタビュー

写真から始まった、映画づくり
野村展代監督が写真家の佐藤竜治とインド・ラダックを訪ね、旅した紀行ドキュメンタリー。ラダックはインド北西部ヒマラヤ山脈の高山地帯にあるチベット仏教最西端の地。今でも多くの人々が自給自足の農耕生活をし、チベット仏教の世界観の中で素朴で温かな暮らしを送っている。現地の生活や食文化、宗教観、家族や友人との繋がりなど、ラダックならではの緩やかで優しい雰囲気が映し出されている。そんなラダックの様子を数年間に渡りカメラに収めてきた写真家の佐藤竜治。彼が映した写真の中の美しい風景に憧れを抱き、佐藤がかつて出会った人々と再会していく旅に同行した野村監督。初めてラダックを訪れた野村の目線で、高地での暮らしぶりや人々の優しさ、ラダックの美しい自然を伝えていく。
写真家の佐藤竜治さんの写真を見られたことがきっかけで、この作品作りがスタートしたということですが、どんな写真をご覧になられてどんな感想を持たれたのでしょうか?
野村展代監督(以下:野村):このフライヤーのメインビジュアルになっている写真をはじめ、最初は風景写真を見せていただきました。それは日本にない岩山や空の青さもそうですが、ほとんど加工していないのに画になっている。他にも人物の写真があり、そこに住む人々が映し出されていました。そこで生活している人の笑顔や、日々を営む姿が映っていて、それが私にはすごく魅力的に感じられました。
「どういう経緯でラダックに行ったの?」と尋ねたことから、現地の方々の生活ぶりを聞いているうちに、入り込んでいってしまったんです。それで「行きたいな」と話したら「行けるよ」て。「飛行機でインドの国内線があるから行けるよ」って教えてくれたました。
ラダックは聞き慣れない地名だったので、こんな場所があったんだと思いながら拝見しました。
野村:ラダックは、インドの連邦直轄領でデリーとかと同じです。普通の映画撮影だと制作のスタッフも同行するのですが、今回は私と佐藤さんだけで行きました。ただ、佐藤さんがカメラを撮ってくださるのですが、写真を撮っている佐藤さんの姿も撮りたかった。機材関連は得意じゃないのですが、自分で撮って自分で編集をしてすごくコンパクトな形での撮影となりました。
実はチベットにも行ったことがなかったんです。本当に知らない状態で一気に進めていった感じです。
撮影で40日間滞在されたそうですが、気持ちの変化などはありましたか?
野村:ラダックに行く前は特に何かがあった訳ではありません。ただ前の作品を撮った時に、師匠の映画監督が急逝されて、ショックを受けたり悲しい思いをしたことで、人の死とかには近い感じてはいたと思います。それを意識して行ったわけではなかったのですが、ラダックに行くとチベット仏教の考えなので、原生は生きているけれどもまた来世も生きるし、今の人生をお祈りして一生懸命、みんな幸せに生きようね、そしてまた次に会おうねみたいな感じなので、その感覚はすごく変わりました。次の世界が見えるというか、これまで来世について考えることが全くなかったので。ラダックにはお祈りをする風習が日常的にあるんです。幸せになるために仏教と共に生活するというのを体験したという感じです。
宗教への意識が日本よりも高いんですね。
野村:名前もお坊さんがつけてくださるそうです。だから似ている名前や同じ名前の方が多くて、菩薩というのがラダック語で「ドルマ」というんですけど、ドルマさんっていう女性がすごく多いんです。町の半分ぐらいはドルマさんじゃないかなって思うくらい(笑)。
ラダックはチベット語ですか?
野村:ラダック語ですね。チベット語と似ています。物の名前も違うものもあれば同じ物もある。想像するに日本での方言の違いのような感じなのかなと思います。あのベースがヒンズー語よりチベット語の方が全然通じますね。
チベット語を勉強していかれたんですか?
野村:それが全然なんです(笑)。佐藤さんに、ラダックに行かれた時は何話で話すの?って聞いたら、片言の英語だって言われていて。ラダックって教育水準がすごく高いんです。インドの本土にはカースト制度とかがあるのですが、ラダックは仏教の思想なのでみんな平等で幸せに生きようという感じなんです。物乞いの人もいないし、小さい頃からちゃんと教育を受けているんです。だから大学生くらいまでの人はほとんど英語が喋れます。私も片言の英語とボディランゲージをすると、それを拾ってくれるんです。おばあちゃんたちは話せないので、その私の片言英語とボディランゲージを通訳して伝えてくれるんです。文法は日本語と一緒ですね。ちょっとずつ単語を繋げるとおばあちゃんにも通じるようになるんです(笑)。
結婚式のシーンがすごく素敵で、印象に残っています。
野村:日本のようにおめでたいことだから外食しようとか、そういうのはあまりないんです。だから自分のおうちにある一番の宝物を持ってきて、着せてくれたり被せてくれたりするんです。そういうのも嬉しいですよね。外の人を排除する感じが全然ないので。そこもチベット仏教の思想だと思いますが、利他主義です。ギブ&テイクじゃなくて、ラダックはギブ&ギブ&ギブって感じですね(笑)。
負のオーラがない感じがしました。嫌な人がいないというか(笑)
野村:そうなんです、ないんです。やっぱり生活環境はものすごい過酷なんです。普通にいるだけでも、日本人だと息が苦しいんです。富士山の上ぐらい高地なので。それにすごく乾燥していますし。おばあちゃんは顔に油をぬっていますけど、私たちも鼻の下とかにワセリンのような保湿剤をぬらないと乾燥して切れちゃうんです。普通にしてても目尻とかが切れちゃうので。昔のラダックの映像とかを観ると暮らすだけで大変なんですよね。今はすごく豊かになっているので、みなさん私たちと同じような洋服を着てて、昔はおばあちゃんが着ているような民族衣装の格好をしていて、布団もないから鳥の羽とか羊の毛にくるまって石をくり抜いたお家で寝てるとか、そういう生活をおそらくおばあちゃんは子供の頃に見ていたと思うんです。
しょうがないですよねこのつまらないこと言ってても、山は低くはならないですから。
監督ご自身は、高山病にはならなかったのですか?
野村:ちょっとだけなりました。デリーから飛行機に乗るときに薬を飲んでいくんです。予防をしていくのですが、レーというラダックの空港に着いた時から2日間くらいは何にもせずにのんびり過ごすっていうそういう時間がないと、かなり危険な感じの高山病になっちゃうので。ラダックのツアーがあるんですけど、そのツアーに参加される方は本格的な高山病になってしまう方も多いと聞きました。町自体は普通の舗装された道だし多少の坂道ぐらいはありますが、本当に歩けなくなるんですよ。でも人間ってすごいもので、40日間もいたら慣れてくるんですよ。行く時は、やっとの思いで歩いていたレーの空港も、帰りはスタスタ歩いちゃってるんです(笑)。
逆に日本に戻ってきてから、違和感はなかったですか?
野村:死生観とかもそうですが、生活自体も全く違っていたので、私自身も少し変わってから帰ってきたんです。すでに不自由な暮らしに慣れ始めてたんですよね。本当に便利ですよね日本は(笑)コンビニもあるしコーヒーもすぐ買えるし、何でもスムーズに出来てしまうことに対して、いいのかな?って思っちゃいました。こんな何でもある暮らしに戻ってきて、大丈夫だろうか?って。
食事も向こうで食べていたものが食べたいなと思って自分で作ったりもしましたが、戻って来てちょうど1年ぐらい経ってるんですけど、ラダックから帰って来てすぐは、細かいことは気にしないおおらかな気持ちだったのに(笑)。
監督としては何か変化はありましたか?
野村:映画監督としては2本目で、監督としての修行をしていたわけではなですし、演出とかのこだわりもあまりないし、だからこそ自分で体験してきたことをそのまま出すというの一番いいんじゃないかな思いました。それは今回の撮影はラダックだったので、景色とかその人に助けてもらったというのがあって、物語を作らなくても物語があるところに行けた。それがよかったなと思っています。そういう体験をしたのを次の作品作りの糧になるだろうと思います。
この作品をご覧になる方に、どう受け取って欲しいということはありますか?
野村:ただただ幸せな気持ちを味わってほしい。不思議でなことに日本とは全く異なる環境ですが、何か懐かしさがあって。チベット仏教の死生観というか、ラダックの方々はその先に次の未来が見えているような生き方をされているので、説明とか押し付けとかではなく、別の世界が広がっていることを知ってもらって、希望を感じていただけるとうれしいです。
11/24(金)公開『JULLAY 群青のラダック』全国ロードショー

【監督】野村展代
【撮影】佐藤⻯治
【公開劇場】中州大洋映画劇場