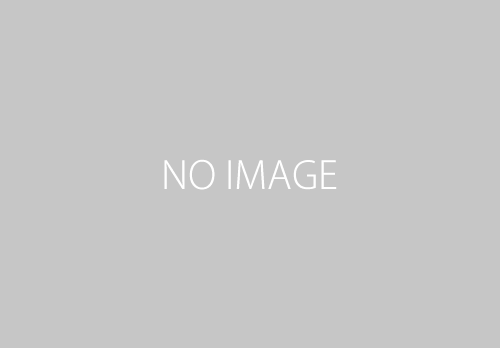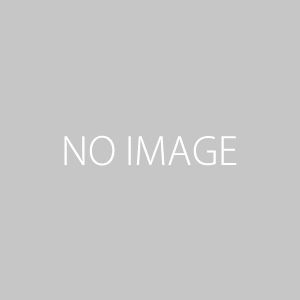約2年ぶりの新刊『四月になれば彼女は』の著者・川村元気インタビュー

2016年、社会現象を巻き起こした映画『君の名は。』、『怒り』、『何者』と数々のヒット映画を作り上げる映画プロデューサーであり、映画化された『世界から猫が消えたなら』や『億男』などのベストセラー小説家でもある川村元気が、最新刊である『四月になれば彼女は』を上梓した。一作目では“死”を、二作目では“お金”と、“自分ではコントロールできないもの”をテーマに描いてきた。そして最新刊となる本作では“恋愛”を描く。
最新刊『四月になれば彼女は』では、現代の大人の恋愛事情が描かれている。そこにあるのは、若者の情熱に任せた瑞々しい恋愛ではなく、愛することを怠った現代のリアルな大人の恋愛。川村は、それをラブレス(恋愛失調)な人たちだと言う。自分にとって本当に大切な人は誰なのか?見ないように、考えないようにしていた愛への劣等感が、感覚が、心の中で沸々と湧き上がる。まさに現代の大人の恋愛事情が“暴かれる”小説となった。
まず『四月になれば彼女は』というタイトルですが、サイモン&ガーファンクルの曲名でもあり、物語の中にも楽曲についての話が出てきます。この曲にインスパイアされて書かれたそうですが、この曲は四月~九月までの半年間の愛を歌った楽曲です。小説も四月から始まりますが、三月まで十二ヶ月で構成されていますよね。そこには何か意図がありましたか?
川村
まさにこの小説のタイトルを『四月になれば彼女は』としたきっかけが、ポール・サイモンがなぜ四月から九月までしか歌わなかったのか、なんです。この歌は、恋愛の一番美しいところをバサッと切り取って終わっていますが、恋愛の大変な部分ってそこからなんです。男女がピークアウトする恋愛を乗り越えて、どう一緒に居るかということが、一番僕らにとってシリアスで切実な問題なのに、そこを歌わなかった。それはどうしてだ!?と思って、その続きを、つまり失われていく恋愛を男女がどう乗り越えていくのかを書こうと思いました。なので、まず“小説の書き方を作る”ことから始めたんです。それに歌の続きを書いた小説ってユニークなものになるんじゃないかと思ったということもありますが。
川村さんは「世界から猫が消えたなら」で“死”を、「億男」で“お金”を、そして最新刊では“恋愛”をテーマにされています。自分の意志だけではどうにもならないものを描きたいと仰っていましたが、それはどうしてですか?
川村
それはおそらく自分が知りたいからなんです。簡単に言うと、インターネットで検索して答えが出るものではないから。ネット検索しても出てこない感情や問題を小説で書きたいと思っていて、恋愛の問題は絶対そこに答えはない。僕自身も解らないから書くことで考える。考えて、なぜ自分たちの恋愛感情は失調してしまったんだろうということに対して、問うてみる。その中で、ある答えを見つけたりする。例えばこの作品では「愛することを、さぼった」という言葉を見つけたのですが、自分でビックリするんですよ。同じように失調している恋愛を感じながら、その答えが見出せない人たちがいっぱいいて、僕と同じようにそういう言葉をみて驚く(ハッとする)現象が起こるんじゃないかなと。読んだ人が似たような集合的無意識で繋がれるかもしてないと思って。自分が解らないから答えを出したいけど、なかなか答えが見つからないものを書こうとしているんだと思います。
コントロール出来ないものを描きたいというところから、今回のサイモン&ガーファンクルにどうやって行き着いたのですか?
川村
小説を書く時は、自分ではコントロールできない3つのものを書くと決めていて、「死」「お金」と書いて、最後に「恋愛」を書くということを決めていました。恋愛小説を書くと決めたら、たくさんの人に「最近恋愛小説は売れないよ」って言われたんです。恋愛小説は売れないの?どうして?と思って、100人くらいに取材をしてみたら、誰も熱烈な恋愛をしていなかったんです。そうか、誰も恋愛をしていないから売れないんだなと。
でも恋愛コミックは爆発的に売れていますよね?
川村
そうなんです。つまり若者の恋愛は売れる。大人の恋愛が売れないんですよ。それって何だろう?と思ったら、大人が恋愛をしていないからだったんです。大人が恋愛をしていないのに、大人が恋愛する物語が溢れている。そりゃ売れないですよ。なぜならそれはファンタジーになってしまうから。そうか、だったら恋愛を出来なくなった人たち=ラブレスな小説を書いた方が新しいし、今のリアルな恋愛なんじゃないかということに行き着いて「四月になれば彼女は」を書くに至ったんです。
小説を書く時は、僕自身がいくつか同時に、別々の場所で気付いている違和感を、ある程度まとめて素材として持ってくる。(その違和感を)寄せに行くというか寄ってくるんですね。例えば恋愛小説を書こうと思ったら誰も恋愛をしていなかったとか、恋愛小説が売れないとか、色んな違和感。なぜ自分は手紙を書かなくなったのか、とか。そしてなぜ、サイモン&ガーファンクルは半年分しか恋愛を描かなかったのかということも。そういう色んな謎が寄ってくる。それぞれ一つずつでも小説になりそうな事象を無理矢理重ねることで、強くてユニークなものができるという自分の中の思想はありますね。なのでサイモン&ガーファンクルも、その違和感の一つだったんです。
この小説では、「写真」「色」「景色」「精神科医」という設定やきっかけになる要素がいくつかありますが、どれも日常的でありながらも非日常感が感じられるものばかりです。それを小説のパーツとして入れようと思われたのはどうしてですか?
川村
必然的に選んだものもあるし、後から気付いたこともあります。まず「写真」は何となく選んだんです。ホントになんとなく。これが小説の面白いところで、何となく選んだものがちゃんと必然になっていく。無意識下で、必然性があるんです。それが小説を書いていて面白いところなんですけど。この中で、フィルム写真をテーマにしようと思って最初に写真家の川内倫子さんに話を聞いたんです。「川内さんは何を撮りたいんですか?」と聞いたら「映らないものを撮りたい」と仰ったんです。あ、それって恋愛感情と同じだと勝手に解釈して(笑)。
フィルムのカメラが今のデジタルカメラと全然違うのは、撮った時に何が映っているのかわからない。現像して観た時に、あの時こういう気持ちだったなとか、こういう顔をしていたんだって気付く。それって全く恋愛感情と同じだと思ったんです。その時は、自分が何を思っているのか解らなくて、終わった時に、あの時こう思っていたと気付く。 「写真」だけじゃなく、他も似た感触のものを別々の場所から引っ張ってきてるんだなと、これも後から自分で気付くんです。サイモン&ガーファンクルという音楽性だったり、シガー・ロス、フェリーニの『道』とか。そういう気分の近いものが全然違う場所から寄ってくる。
恋愛小説だと言われれば、恋愛小説ですが、現代の人間ドラマのようにも感じます。
川村
僕は向田邦子さんの作品が大好きなんですけど、向田邦子さんの作品って恋愛感情を丁寧に描いたものが多いんですよね。だけど、最終的には今の人間の欲望や失ってしまったものを描いていて、それは近しいものがあるなと思っています。恋愛のフィルターを通すと、途端に現代の人間が失ったものとか、欲しがっているものが見えてくる。なのでこの小説でも恋愛を通して、僕が感じている現代人の本当の姿を浮き彫りにできたらと思っています。
物語の中に、いくつか映画作品が出てきます。何か決めて選ばれたのですか?
川村
割と散文的に選んでいるんですけど、ひとつ決めていたのは、ハルというキャラクターをフェデリコ・フェリーニ監督映画『道』のヒロイン・ジェルソミーナにするということでした。死をもって生を証明するし、恋愛感情ということと死ぬということは近いというか。この人の人生には何も良いことがなかったんじゃないかと思える人の方が、最終的に決定的なものを見つけているみたいな。僕はどうしてもジェルソミーナ崇拝があるので(笑)、で、ザンパノみたいなヤツが、色んな人から色んなものを奪ったけど、結局何も手に入れられなかった、みたいな。あの感覚を描きたかったんですね。
作品に出てくる映画は『エターナル・サンシャイン』『道』『her/世界でひとつの彼女』『卒業』など。どれも恋愛映画ですが、どれも違うタイプで、いびつな恋愛というか普通の恋愛物語ではないですよね。それらを選んだ理由はあったんですか?
川村
確かに恋愛の失調を描いている作品ばかりです。永遠に愛し合う二人、ではなく上手に愛せない二人を描いた作品ばかりです。今のラブストーリー作品というのは、映画が最先端だと思っているんです。小説でも漫画でもアートでもなくて、映画が一番先鋭的。『ブルー・バレンタイン』や『世界にひとつのプレイブック』もそうですし、それこそ『her』や『エターナル・サンシャイン』って、あんなに尖った表現で、今の恋愛の真実に迫っている。だから今回ラブストーリーを描くと決めた時に、今の映画人たちと勝負したい、という気持ちはありました。何をもって、恋愛の最先端を描くか。
今回小説に於いて言うと、ラブストーリーと言っておいて、読んでみたらラブレスという恋愛の失調を見せる。読者の心が、階段から足をガタッと踏み外すみたいな感覚になってくれるといいなと思って書きました。だからそう感じられる構成にしています。すごく恋愛が盛り上がった次の瞬間に、パッと場面が変わり、全く愛が冷め切った主人公が結婚式の打ち合わせを何の興味も無くやっている、みたいな。ああいう階段がゴソッと抜けた時のショックみたいなことを繰り返したいと思っていました。それは成功したんじゃないかなと思います(笑)。
川村元気(かわむら・げんき)ーーKawamura Genki
1979年横浜生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業。『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』『バクマン。』『バケモノの子』『君の名は。』『怒り』などの映画を製作。2011年に優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞。12年には初小説『世界から猫が消えたなら』を発表。同書は本屋大賞へのノミネートを受け、130万部突破のベストセラーとなり映画化された。他著作として、中国での映画化も決定した小説第2作『億男』、絵本『ティニーふうせんいぬのものがたり』『ムーム』『パティシエのモンスター』、対話集『仕事。』『理系に学ぶ。』『超企画会議』など。

四月になれば彼女は
川村元気・著
定価:本体1,400円+税
判型:四六判