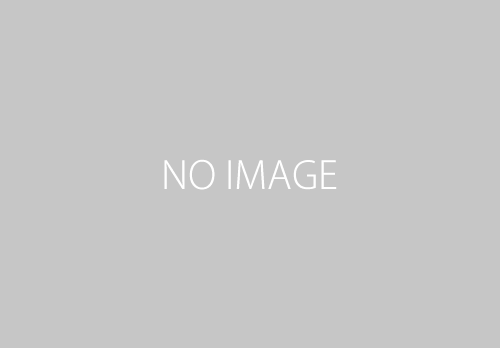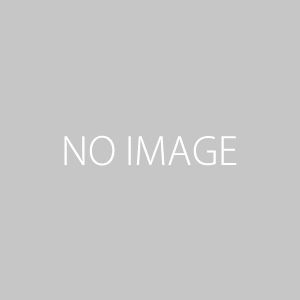コラム・岩井の好きな映画 vol.55「主戦場」「沈没家族」
シアタービューフクオカで絶賛連載中のハイバイ・岩井秀人氏のコラム「岩井の好きな映画」。本誌と併せてお楽しみください!

ハイバイ・岩井秀人コラム【岩井の好きな映画】vol.55「主戦場」「沈没家族」
ドキュメンタリー「主戦場」は、ぜひみんな見てみてほしい。「政治絡みのことはちょっと、、」と思っている人でも大丈夫。なんせ監督自身が元々YouTuberで、「なんだか日本の戦時中のことで言い合ってる人がいるなあ」という興味から調べていったという流れがそのまま描かれているので、難しくなく色々と考えられる。あとは超面白いのが、第二次大戦(太平洋戦争)で日本がアメリカに「勝った」ことになってる人が登場する。彼を見るだけでも価値ある。
もう一つもドキュメンタリーの「沈没家族」。これがもう、現象として非常に複雑だった。題材は超面白い。中野のある母子家庭の母親が、一人息子を育てるのに「コドモ育ててみたい人、募集!」とチラシをまいた。そして集まった「育てたい人たち」が交代交代で、その家の息子「土(つち)君」を育てる。土君は中学生くらいになってようやく、自分の家族が一般的なそれではないことを知る。周囲からはやんわりと「母親の責任が果たされてない」とか「育児放棄」的な言葉が聞こえてくるが、土君自体はとても幸せに育つ。母親はこの見ず知らずの親たちと自分たちのことを「沈没家族」と名付けた。この土君自身が監督を務め、大学の卒業制作で製作されたドキュメンタリーなんだけど、上にも書いた通り、現象として「沈没家族」という行い?営み?はとても面白いし、現在の「親がなるべく誰の世話にもならずに子供を育てられないと失格」な空気に一矢報いる、非常に「現代の家族のあり方」について考えられる素材だ。この「現象」としての「沈没家族」は、実は日本には昔から存在していた。「長屋文化」というやつだ。住居が連なったアパート的な家に、いくつもの家族が住んでいて、そこでの生活は現代の「お隣さんの名前さえ知らない」の逆をいく、「まあ、あんた忙しい時はあたしたちがお子さん見るから」といったことを相互補助して生活していたもので、これを少し変わったやり方で達成したものが「沈没家族」だということだ。だからして、社会的には「変わった育ち方」をしている土君だが、本人自体はいたって幸福であり、なんら特徴というか、癖も何もなく、フラットな人物だ。幼少期から多様な大人たちに囲まれ、自然と緩やかに「相互監視システム」も働くわけでDVが起きるわけもなく、子供が育つにはこれ以上ない環境なのだ。僕が不満に思ったのは、そこなのだ。本人が、その「価値」についてあまりにも無自覚なのだ。せめて外の社会で「沈没家族」がどう受け取られているか、いわゆる「社会」の目線を入れるなどしてから、”Inter View”に入って欲しかった。土君自身の「うちがどうも変わってる様だ」というぼんやりしすぎの動機だけで「親たち」に取材するから、「どう思ってました?」「僕どうでした?」といった質問しかできず、という時間が続く。僕自身が「自分史を作品にする」ということをしてきた立場だから思うことがある。「題材にもっと敬意を払ってくれ」である。作り手が自分の存在自体について考えられる機会は、そうそうない。「沈没家族」について作品を作る機会も、そのことについて人々に考えてもらうきっかけも、なかなかない。「育ての親たち」との時間が、なんとなく過ぎていってしまっている。全てのシーンに、「こうしたい」という「作家性」がなく、「なんかないかな?」なのだ。と、「作家性」の様なものについて色々と考えていて、また思うこともある。そうか、作家性も育たないほど、フラットで、途轍もなく「フツー」の自尊心を持ったが人物が育ったのが、その「沈没家族」なのだ。「沈没家族」が全然「沈没」なんかしてないことを、身をもって証明している。学歴も経済環境もいいけど「沈没」している家族が散見する中、土君は、その生き証人なのだ。
でも、だからこそ、もうひと踏ん張り、ふた踏ん張りして欲しかったと思えて仕方がない。君をその道に導いてくれた、今まで見てきた映画、ドラマ、ドキュメント、そこにその作品を並べていいのか?と、自分自身に問うて欲しい。
●いわい ひでと/1974年生まれ。劇作家・演出家・俳優、ハイバイのリーダー。「ある女」で第57回岸田國士戯曲賞を受賞。
◎シアタービューフクオカ vol.79掲載(2019.6発行)